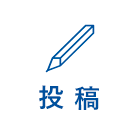不動産投資を始めたら、後から物件にシロアリ被害の形跡が見つかった・・・。そんなとき、物件の買主はどう対応するべきでしょうか。
実は不動産の売買契約では、買い手が不利にならないようにさまざまなルールが法律で規定されています。その1つが、購入した物件に欠陥があった場合に売主が責任を負う「瑕疵担保責任」です。
瑕疵担保責任は、2020年4月1日より民法の改正により「契約不適合責任」と名前が変わっています。瑕疵担保責任や契約不適合責任の知識は、投資用物件だけでなくマイホームを購入するときにも役立ちますので、ポイントをおさえておきましょう。
瑕疵担保責任とは? 改正民法による変更点も解説
瑕疵担保責任とは、購入した不動産に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合に、売主が責任を負うことです。
例えば、購入したマンションで雨漏りが発生した場合、一定期間内であれば買主は売主に対する損害賠償請求や売買契約の解除ができます。瑕疵担保責任においては、売主が建物の欠陥を意図的に隠していた場合だけでなく、その欠陥を知らなかった場合も買主からの請求に応じなければなりません。
ただし、買主が購入時に瑕疵の存在を知っていた場合は、売主に対して請求できないとされています。
20年4月の民法改正に伴って制定された契約不適合責任では、売主が負うべき責任や買主が請求できる内容が変更されました。
例えば、購入した物件で雨漏りが起きていることを買主が知っていても、売買契約書や重要事項説明書に雨漏りについての記載がなかった場合は、売主が責任を負うことになる……というもの。
瑕疵担保責任の考え方では、瑕疵が隠れていたかどうかを立証するのが困難でした。そこで改正後の民法では「隠れた瑕疵」という表現を削除し、瑕疵が「契約時に明らかであったかどうか」をポイントとしているのです。また買主は、損害賠償の請求や契約の解除に加えて、住宅の修繕や売買代金の減額についても売主に請求できるようになりました。
「瑕疵」=注意しても発見できない欠陥
瑕疵とは、住宅に関する一般的な知識を持つ買主が、注意しても発見できないような欠陥のことを指します。代表的な瑕疵の例は以下の通りです。
・雨漏り
・シロアリ被害
・給排水管の故障
・建物構造上主要な部位の木部の腐食
・土壌汚染
・地盤沈下
・事故物件
・隣の部屋がゴミ屋敷であるなどの心理的瑕疵
契約不適合責任の考え方では、買主が瑕疵の存在を知っていても、契約書などに瑕疵の存在が明記されていなければ売主が責任を負うことになります。
瑕疵を保証する「資力の確保」が義務付けられる宅建業者
売主が宅建業者(不動産会社)である場合、買主が不利にならないように瑕疵について保証を行うことが法律で義務付けられています。具体的には、新築物件か中古物件かを問わず、物件が買主に引き渡されてから最低2年間は、建物の以下2つの部分に対する瑕疵を保証しなければなりません。
- 構造耐力上主要な部分:梁や柱など
- 雨水の侵入を防止する部分:屋根や外壁など
また新築物件を購入した場合は、瑕疵に対する保証が10年間となります。さらに新築住宅を供給するハウスメーカーや工務店は、住宅瑕疵担保責任保険への加入や保証金の供託などによって住宅を保証する資力の確保が義務付けられているため、安心と言えるでしょう。
中古物件を購入する場合の注意点
個人間の物件売買では、新築物件のような長期の保証は受けられません。売主が個人の場合は、買主との合意があれば瑕疵保証を設定できますが、保証期間はどんなに長くても1年程度。数カ月ということも少なくありません。また、売主が宅建業者であっても、中古物件について2年を超える瑕疵保証を受けるのは困難です。中古物件への投資を行うときは、売主が加入している保険や提供しているサービスに注目してみましょう。
売主が瑕疵保険(既存住宅売買瑕疵保険)に加入していると、物件が引き渡された後で不具合が発覚した場合に、最大で1,000万円の保険金が支払われます。保険期間は最長5年間。瑕疵保険で保証されるのは、通常の瑕疵保証と同じく「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」ですが、給排水管などの保証を追加することもできます。
瑕疵保険に加入している売主から物件を購入することで、購入後に欠陥が発覚した場合でも保険によって保証を受けられるため、買主の安心につながります。
また不動産会社によっては、住宅に精通したプロが住宅の劣化状況や欠陥の有無を診断する「ホームインスペクション」を提供しています。ホームインスペクションが実施された物件は、一定の安全性や性能が証明されているため、買い手はさらに安心できるはずです。
まとめ
不動産の売買では、買主が不利にならないように法律や制度で守られています。
民法が改正され「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に変わったことで、隠れた瑕疵でなくても、買主は売主に対して保証を請求できるようになりました。
新築物件の場合、供給する事業者は保険への加入や保証金の供託によって、瑕疵を保証する資力の確保が義務付けられているため安心です。ただし中古物件の売主にはそのような義務が課せられていないため、保険の加入状況などに注目して、より慎重に物件を選ぶ必要があることを覚えておきましょう。